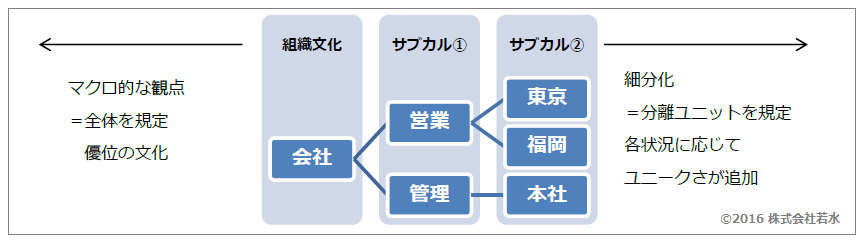強い組織文化
組織文化には強弱の程度がある。
その強弱は、次の2つのポイントによって決まる。
①文化の影響力
組織が持つコアとなる価値観が、ひとつの組織文化としてメンバーに対してどの程度の影響力を持っているか
②文化の共有範囲
コアとなる価値観を受け入れ、共有しているメンバーの数
たとえば、ある企業が「顧客への情報開示は積極的に行い、オープンにすることが望ましい」という価値観を掲げているとする。
上記の2つのポイントを基準に考えると
①文化の影響力
従業員が、実際に顧客に対して良い・悪い情報にかかわらずどの程度の頻度で顧客に対してオープンな行動を取っているか
②文化の共有範囲
オープンな行動をしている従業員がどれくらいの人数いるか
このように、行動の頻度と人数に比例して組織文化の強弱は測ることができ、組織マネジメントにおいて経営陣が掲げている価値観が有効かどうかを把握する手がかりとなる。
強い文化は離職を防ぐ
組織が強い文化を持つと、メンバーが行動や思考の拠りどころとする基盤が築かれることになり、そうした基盤の上にメンバーは一致団結し、組織に対して忠誠心を示したり、組織への関与を高めたりする。
明確で広く共有されている組織文化に従って行動することで、メンバーは確実に成果を挙げ、賞賛や評価を受けられる可能性が高くなる。
成果が挙がり、生産性が高まって「今日はいい仕事ができた」と思えると、職務への満足度が上がる。さらに周囲からの信頼や評価が高まると仕事がおもしろく感じられ、離職率は下がると考えられる。そして、組織文化に対するコミットメントがさらに強まり、好循環を生む。
もちろん、職場環境や待遇面の影響もあるだろうが、組織文化の強さという側面からメンバーの忠誠心や会社愛を見ることも可能である。
弱い文化
逆に、組織において拠りどころとなる価値観が、あいまいであったり、不明確であったりすると組織文化は弱くなる。
たとえば、経営理念として「顧客のために」という言葉を掲げていても、実際は社長や上役の顔色をうかがって社内にベクトルを向けなければならない雰囲気があれば、一貫性を欠いており、もはや経営理念が立派に書かれたものは紙くず以下の存在でしかない。
弱い文化が組織内にはびこると、離職が起こる可能性が高くなる。
なぜなら、掲げている理念や繰り返される言葉に対して、現実に求められるものがずれていれば、メンバーは行動の指針を失い、評価も不明確になってモチベーションが下がるからである。
強い文化は、ある種宗教的に強い存在力と影響力を持ち、メンバーの行動・思考様式を規定している。そのため、変化に対しては抵抗を示すが、弱い文化であれば変革や改革のチャンスが潜んでいる(上役の顔色を伺って「ノー」と言わないことが良い価値観とされ、それが暗黙のうちに広く共有されていれば、それはそれでひとつの強い文化となっており、変化は難しい)。
本説明文は(株)若水の作成によるものです。 転載・転用・問合せをご希望の方は下記フォームよりご一報ください。 また、本説明文は弊社の解釈にもとづき執筆されています。 雑誌記事や論文等による学術性を保証するものではありません。