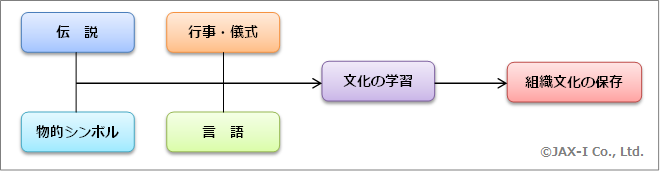コンフリクトとは
コンフリクト(conflict)は、元々は「武力対立」、「紛争」、「主義・主張の争い」、「心の葛藤」「矛盾」を意味する。
コンフリクトを組織という観点で見ると、人と人の対立や部門間の摩さつなどがイメージしやすい。なぜなら、実際に人間関係の悪化や、縦割り組織における部門同士のあつれきは必ずと言ってよいほど存在し、それが組織のパフォーマンスに影響を与えていることを、組織内のメンバーが認識しているからである。
しかし、対立や摩さつが必ずしも悪い結果にばかりつながっているわけではない。ここでは、「コンフリクト=悪いもの」という思い込みをいったん無くしたうえで、組織で用いるコンフリクトを次のように定義したい。
①組織内のメンバー間、または、部門間で生じる対立や不一致、摩さつなどの相互作用であり、
②その当事者全員が、対立等の存在を認識していること。
ここでのコンフリクトには、目標の不一致や事実の解釈をめぐる相違、期待する行動に関する食い違い、明らかな行為や暴力、意見の対立といった幅広いものを含む。仕事の進め方の相違、主張や考え方の対立、利害関係の不一致なども一般的に想定される。
また、継続的な活動を行う中で、メンバーや部門間の相互作用が「ある一線を越え」、コンフリクトに発展する時点があると考える。たとえば、ひとりのメンバーだけが何か影響を与えようと行動したとしても、それが空振りに終わり、誰も見向きもしない状況であれば、コンフリクトがあるとは言えない。
コンフリクトに対する3つの見方
コンフリクトは様々なとらえ方が可能であり、大きく次の3つに分けられる。
①自然とするとらえ方
コンフリクトは、あらゆる集団および組織で自然に起こるものと考える。
コンフリクトは避けられないのだから、コンフリクトを受け入れるよう訴える。コンフリクトは排除できないが、ある場合には業績にメリットをもたらすことさえあると主張する。
②奨励するとらえ方
組織においては、良い種類のコンフリクトを奨励すべきだと考える。
調和的で平穏、協力的な集団は停滞しがちであり、変化や改革の必要性に対して無関心かつ鈍感になりやすいというのが根拠(事なかれ主義の回避)。
集団のリーダーに集団を活性化して、自己批判する姿勢を持たせ、創造性を発揮するためには最小限のコンフリクトが必要であり、それを維持すべきと考える。
③否定的なとらえ方
コンフリクト=悪という、否定的な見解。あつれきや衝突、不合理といったマイナスの側面を重視し、コンフリクトは避けるべきものと考える。
コミュニケーションのまずさ、信頼のなさ、上司が部下の期待に応えられないといった機能不全が原因とする。コンフリクトはすべて避けなければならないと考えるので、コンフリクトの原因に注意を向け、問題を解決すればよいとする。
しかし、コンフリクトを減らすアプローチは必ずしも組織のパフォーマンスにつながらないとされている。
したがって、組織がコンフリクトに対して否定的なとらえ方に固執していると、パフォーマンスにつながらない無駄な時間やエネルギーを使うことになったり、議論や問題解決が避けられてしまったりする可能性がある。
コンフリクトの種類
コンフリクトには良いコンフリクトと、そうでないものがある。
コンフリクトを奨励するとらえ方では、コンフリクトの種類を区別して、集団の目標達成を支援し、業績を向上させるような生産的で建設的な形の「生産的コンフリクト」を奨励している。
逆に、組織のパフォーマンスを下げてしまう「非生産的コンフリクト」もあり、基本的にそれは避ける姿勢となる。
①業務コンフリクト
仕事の進め方や内容、業務目標について、議論や問題提起を行い、当事者には意識的に仕事に取り組んでもらうことが目的であり、生産的コンフリクトと考えられる。
業務コンフリクトが機能するには、仮説にもとづいた議論をもとに検証と振り返りを行って、改善する態度が必要であって、議論ばかり行うようなコンフリクトはかえってパフォーマンスを低下させてしまう可能性がある。
組織のパフォーマンスをを向上させることを第一の目的としており、業務のあり方やプロセス、仕事の割り振り、責任の明確化、目標などを焦点にして話を進めるため、議論のゴールが見えやすく一致しやすい。
多くの場合、「誰が言ったか」など人とからめて考える傾向があるため、仕事の話で議論をしていても、いつの間にか人の問題になり、非生産的コンフリクトに移行してしまう。
業務コンフリクトは、仕事に役立つアイデアを議論し、場を活性化させることにつながるため、パフォーマンスに常にプラスの影響を与えるものであり、奨励すべきものである。
②対人コンフリクト
人間関係のあつれきや摩さつのことを指し、ほとんどの場合は非生産的である。
人間関係の悪化はメンバー同士による対立や衝突が増えてしまい、相互理解が進まなくなってしまう。
その結果、組織における仕事の進行や完結を妨げ、パフォーマンスを低下させる。
メンバー同士の相性やそりが合わなくて、お互いをライバル視して競争するパターンも見られる。このとき、お互いの仕事を邪魔したり、横槍を入れて自分の利益になるような行動を行うと、非生産的コンフリクトが発生する。
しかし、ライバル心を基本にして、目標達成やプロセス改善にのみメンバーが注力して競争すれば、パフォーマンスは高まると考えられる。
このような現実的な人間関係をもとにしたマネジメントの考え方は、組織のデザインや職務プロセスの設計に関係するところとなる。
本説明文は(株)若水の作成によるものです。 転載・転用・問合せをご希望の方は下記フォームよりご一報ください。 また、本説明文は弊社の解釈にもとづき執筆されています。 雑誌記事や論文等による学術性を保証するものではありません。